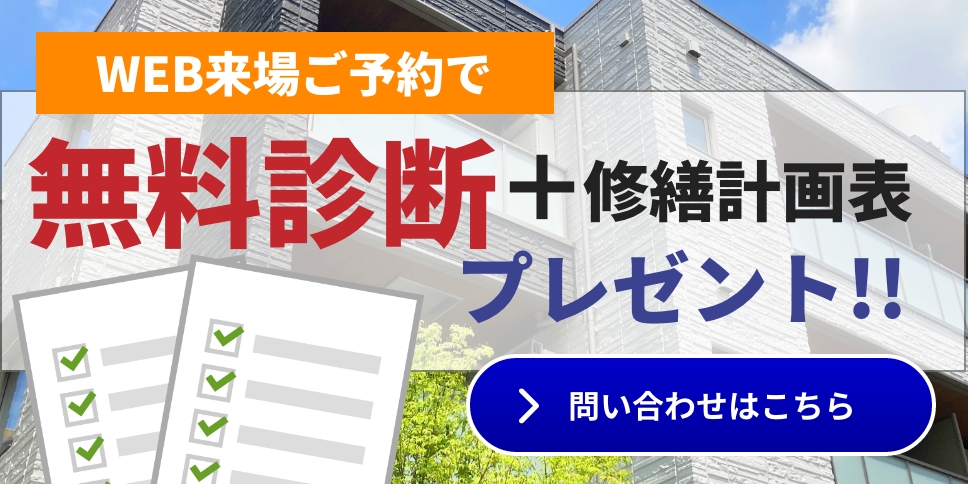こんにちは!東京都の大規模修繕専門店オーナーズプラスです。
「修繕積立金が足りない…」と悩んでいるオーナー様は決して少なくありません。築20年以上経過したアパート・マンションでは、大規模修繕の時期が迫っているにもかかわらず、積立金が計画通りに貯まっていないという事例が増えています。
この記事では、修繕積立金が不足するとどうなるのか、原因とリスクを専門的に解説したうえで、大規模修繕の前にできる3つの現実的な対処法を紹介します。
※【品川区】地域密着型の大規模修繕会社を選ぶメリットについて詳しく知りたい方は
【品川区】地域密着型の大規模修繕会社を選ぶメリットをご確認ください。
※東京都のウレタン防水工事 通気緩衝工法のメリットと施工手順について詳しく知りたい方は
東京都のウレタン防水工事 通気緩衝工法のメリットと施工手順をご確認ください。
Contents
修繕積立金が足りないとどうなる?放置のリスクとは
修繕積立金が不足している状態を放置すると、建物の価値や入居者満足度に深刻な影響が及びます。特に「先延ばしにすれば何とかなる」と考えるのは非常に危険で、長期的な損失を招く可能性が高いです。ここでは、主なリスクを2つの視点から解説します。
修繕工事の延期による建物劣化の加速
修繕積立金が足りず工事を延期すると、建物の劣化スピードは一気に加速します。外壁のひび割れや防水層の剥離は、放置するほど水の侵入経路を増やし、鉄筋コンクリート内部の腐食や爆裂といった深刻な構造劣化へと進行します。
例えば、通常12年周期で行われる外壁改修を5年延期した場合、補修費用が1.3倍〜1.5倍に膨れ上がるケースが少なくありません。雨水が内部へ浸入すると、単なる塗装では対応できず、下地補修や鉄筋補修といった高額な追加工事が必要になるためです。
私が担当した築28年の賃貸マンションでも、資金不足を理由に大規模修繕を3年間先送りした結果、外壁タイルの剥落と躯体コンクリートの中性化が進み、当初予定より約600万円も工事費が増額しました。このように「先送り」は、結果的に大きな損失を生むことが多いのです。
資産価値の低下と住民トラブルの可能性
修繕が遅れると、資産価値の低下は避けられません。外壁の美観が損なわれ、エントランス周りが老朽化すると、入居者の印象は大きく下がります。設備や共用部の不具合が放置されると、「管理が行き届いていない物件」として評価が下がり、空室率が上昇する可能性も高まります。
また、劣化による雨漏りや漏水事故が発生すると、入居者とのトラブルにも発展します。「共用部の不具合が原因で室内に被害が出た」として賠償請求を受けるケースもあり、管理組合やオーナーの責任が問われる事態になりかねません。
このようなリスクを避けるためにも、修繕積立金不足を「今すぐ向き合うべき課題」として捉えることが重要です。
修繕積立金不足の原因を知ろう
修繕積立金が足りない理由は、「思ったより工事費が高かった」という単純な問題だけではありません。多くの物件で共通して見られる3つの根本原因を理解することが、対策の第一歩です。
長期修繕計画とのズレ
最大の原因は、当初立てた長期修繕計画と現実の工事費用とのズレです。計画時に想定した工事単価が、10年・20年後には物価上昇や人件費高騰によって大きく変わっているケースがほとんどです。
国土交通省の調査によれば、外壁改修・防水工事の平均単価は2010年から2024年にかけて約1.4倍に上昇しています。この差が積立額と実際の必要額のギャップを生み、資金不足の原因となっているのです。
また、当初は予定になかったエレベーター更新や給排水管の更生工事といった「追加工事」が必要になることも珍しくありません。これらを考慮しないまま計画を放置すると、積立金は確実に不足します。
段階増額方式による初期積立不足
多くの管理組合では、入居当初の負担感を抑えるために「段階増額方式」を採用しています。初期段階では低めの積立額を設定し、数年ごとに徐々に増やしていく方法です。しかし、初期積立額が低すぎると、工事時期が来たときに資金がまったく足りないという事態が起こります。
特に築20年以上経過した古いマンションでは、初期段階で積み立てた額だけでは総工事費の半分にも満たないケースも少なくありません。増額のタイミングを誤ったり、増額自体を先延ばしにしたりすると、その影響はさらに深刻になります。
管理組合の資金管理の甘さ
もう一つの原因は、管理組合の資金管理が十分でないことです。修繕積立金の運用状況や将来的な支出見込みを定期的にチェックせず、漫然と管理しているケースは意外と多いのが現実です。
例えば、積立金の一部を他の用途に流用してしまったり、長期修繕計画の見直しを10年以上行っていなかったりすると、必要額との乖離が急速に拡大します。管理組合が専門家と連携し、定期的に計画と現状を照合する体制を整えることが重要です。
大規模修繕前にできる3つの対処法
修繕積立金が不足していても、大規模修繕を諦める必要はありません。オーナーや管理組合が現実的に取れる手段は主に3つあります。それぞれの方法はメリットとデメリットがあり、物件の状況やオーナーの意向に合わせて選択することが重要です。
一時金の徴収で不足分を補う
修繕積立金が不足している場合、最も直接的な解決策が「一時金の徴収」です。入居者や区分所有者から追加で資金を集め、不足分を補う方法です。
例えば、総工事費が1億円で積立金が7,000万円しかない場合、不足分の3,000万円を一時金として徴収します。区分所有者が30世帯であれば、1世帯あたり100万円の負担となります。
この方法の強みは、借入や工事範囲の縮小をせずに、本来必要な工事内容を計画通りに実施できる点です。修繕の質を落とさず、建物の資産価値を守ることができます。
しかし、実際には一時金徴収は合意形成が難しく、特に賃貸物件や投資用マンションでは「一度に大金を出すのは負担が重すぎる」と反対する所有者が多く出る傾向があります。私が関わった管理組合でも、一時金として80万円を徴収する提案をしたところ、半数以上の区分所有者が反対し、最終的に借入と組み合わせる形で落ち着きました。
そのため、一時金徴収を選択する場合は、事前に資金不足のリスクを数字で示し、長期的にどれだけ得になるかを丁寧に説明することが必要不可欠です。
金融機関からの借り入れで資金調達
2つ目の方法は、金融機関から融資を受けて不足分を補う方法です。管理組合名義で借り入れが可能な金融機関も増えており、返済期間を10〜15年程度に設定して毎月の積立金と合わせて返済していく仕組みです。
例えば、3,000万円の不足分を年利2%、15年返済で借り入れると、毎月の返済額は約19万円となります。30世帯であれば1世帯あたり月6,300円の負担増です。一時金として100万円を一括で徴収するのに比べれば、負担は分散され、心理的にも合意が得られやすいのが特徴です。
また、金融機関によっては「大規模修繕専用ローン」や「修繕積立金借入専用プラン」といった商品もあり、担保不要で借りられる場合もあります。東京都内では信用金庫や都市銀行が積極的にこの分野に取り組んでいます。
ただし注意点として、返済期間中は積立金の自由度が下がるため、次の大規模修繕までに再び資金不足に陥るリスクがあります。また、返済利息分だけ総額の支払いが増えることも事実です。資産価値を維持しながらも長期的な負担をどうコントロールするかがカギとなります。
工事内容の見直し・分割施工でコスト調整
3つ目の方法は、工事内容を見直したり、複数年に分割して施工することで費用を調整するやり方です。必要な工事をすべて同時に行わず、優先度の高い工事から順番に実施していく方法です。
例えば、外壁改修・屋上防水・鉄部塗装を同時に行うと総額1億円ですが、今年は外壁改修のみ7,000万円を実施し、屋上防水は3年後に3,000万円で行う、といった形です。
この方法の利点は、一度に多額の資金を用意する必要がなく、工事を進めながら資金を補充できる点です。所有者の合意形成もしやすく、現実的な落としどころとして採用されるケースも多いです。
しかし、分割施工には「足場の設置を複数回行う」という大きなデメリットがあります。足場設置費用は工事費全体の15〜20%を占めるため、2回・3回と分けて工事を行うと、トータルのコストが大幅に増える可能性があります。また、工期が延びることで入居者の生活に支障が出やすい点も懸念されます。
対処法のメリット・デメリットを比較
どの方法を選択するかを判断するためには、メリットとデメリットを冷静に比較することが必要です。ここでは3つの方法をそれぞれ掘り下げます。
一時金徴収の合意形成の難しさ
一時金徴収の最大のメリットは、追加の利息負担や工事内容の削減が不要で、当初計画通りに大規模修繕を実施できる点です。結果として建物の資産価値がしっかりと維持され、長期的には空室率低下や修繕費増加を防ぐ効果があります。
一方で、短期的な負担額が大きいため、所有者間で不公平感が生まれやすく、合意形成が非常に難しいのが現実です。特に賃貸オーナーは「修繕費を回収できるまでに時間がかかる」と考え、支払いに消極的になることが多いです。
借り入れによる返済負担と資産価値への影響
借入は、資金調達のハードルを大幅に下げ、工事の品質を落とさずに実施できる現実的な方法です。分割払いに近い仕組みのため、所有者の合意も得やすいのが特徴です。
しかし、返済中は積立金の運用に制約がかかり、次回修繕に備える余裕が減少します。さらに、長期間の利息負担により総支払額が増加することも避けられません。そのため、借入を行う場合は、次回修繕に備えた積立金の増額を同時に行うことが必須です。
分割施工による工期延長と生活負担
分割施工は「目先の資金不足を解消する」点で非常に有効です。所有者や入居者の合意が得やすく、資金調整の柔軟性も高いです。
一方で、足場費用が重複することによる総コストの増加、工事が長期化することで入居者にストレスを与えるといったデメリットがあります。さらに、優先順位を誤ると重大な劣化が進行し、かえって高額な補修費を招くリスクもあります。
まとめ
修繕積立金が足りない状態で大規模修繕を迎えるのは、多くのアパート・マンションで共通する課題です。放置すれば建物の劣化が加速し、資産価値の低下や入居者トラブルを招くリスクがあります。
不足の原因は「長期修繕計画とのズレ」「段階増額方式による初期積立不足」「管理組合の資金管理の甘さ」にあることが多く、それぞれを正しく理解することが解決の第一歩です。
対処法としては、
-
一時金徴収で不足分を補う
-
金融機関からの借り入れで分割負担にする
-
工事内容を見直して分割施工する
の3つがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。オーナーや管理組合は、物件の状況や所有者の意向に応じて最適な方法を選び、将来を見据えた資金計画を立てることが大切です。
東京でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!
大規模修繕・マンション工事・防水工事のオーナーズプラスでは、東京でお客様にピッタリのプランを提案しています。
東京のアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事はオーナーズプラスお任せください!!
私が担当しました!

営業
猪股 浩二猪股 浩二
私は建築業の仕事に30年以上携わり、現場管理を通して、戸建て物件から大規模修繕までを担当してきました。様々なケースに携わってきましたが、共通して、これまでの建物に対する不十分な施工やメンテナンスが手遅れになってしまっている案件が多いと感じています。 いち早く修繕について検討して頂けるよう、専門家としてオーナーの皆様により多くの情報を提供してまいります。